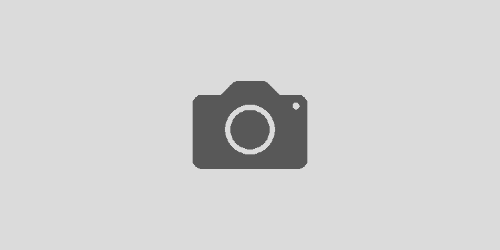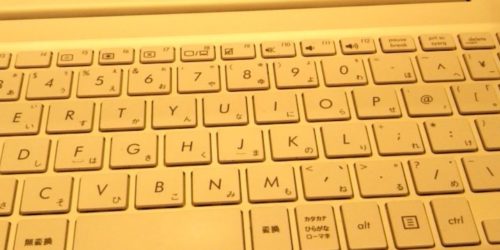「勉強が好きな子どもたち」という欺瞞
「勉強が大好きな子ども像」への違和感
みなさんこんにちは。あなたの街の文系男子、トム・ヤムクンです。
「道徳の教科書に登場するパン屋が『郷土愛を盛り込まなくてはならない』という理由で和菓子屋に変えられた」という話がいっとき、話題になりましたが、今日はそんな学校の教科書のお話です。
みなさん、ご自身が小中学生のときの国語の教科書などを思い返してほしいのですが、一定の頻度で「勉強が大好きで、先生どころか親にも敬語を使う良い子」ばかりが出てきませんでしたか?
例:たかしさんはお父さんと水族館にでかけました。
たかしさん「『魚』という漢字は、魚の形に似ていますね」
お父さん「よくきがついたね。魚という字は、魚の形に似せられて作られたんだよ」
みたいな。
僕はあれに、ものすごく違和感を持っていました。
こういう子ども像を教科書に掲げることは、現実の我々の認識とかなりかけ離れているために、教科書への子どもや一般市民の信頼度を非常に大きくそこなっているのではないでしょうか。
「昔の人は勉強に励んでいた」というイメージ
この本を見てください。
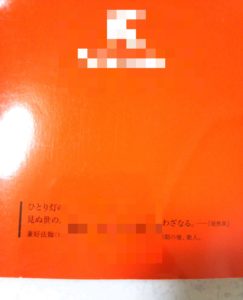
これは大学受験生たちに大人気の某赤本の裏表紙なのですが、ここには古今東西の「勉強」とか「受験」とかに関する著名人の名言が書かれています。
「昔の人の勉強に関するありがたいお言葉を呼んで、チミたちもお勉強を頑張り給えよ、わっはっは」ということなのでしょうが、ここに掲げられている文の一例がこちらです。
ひとり灯のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするこそ、こよなう慰むわざなる。
これは『徒然草』に収められた兼好法師の言葉です。「明かりの下で書物を広げて、昔の人とまるでお友達になったような気持ちになるのはとっても心安らぐことだなあ」みたいな意味です。
この文章じたいを否定する気はさらさらないのですが、この赤本の編集者はこの文章を、あきらかに「お勉強って楽しいなあ」っていう文脈で扱ってますよね。
受験生にとっては、「いや、楽しくないし、必要だからやってるだけだし」というものではないでしょうか。
このような「子ども像」「昔の人像」が違和感を抱かせる理由は?
1.「子どもは勉強が嫌いである」という我々の感覚に恐ろしく合致しない
勉強が嫌いな子どもって多いですよね。
あるいは、勉強が好きな子どもも多いのかもしれませんが、フィクションは勉強が嫌いな子ども像を再生産し続けています。その代表格が野比のび太であることは言うまでもありません(笑)
それらが、「子どもは勉強が嫌いである」というイメージを子どもたち自身のなかに刷り込んでいるのです。
極端なことを言えば、「勉強が苦手だけどスポーツができて話が面白い奴」と、「勉強ばかりしていてメガネかけてて友達が少ない奴」(ひとまず男子に限った話をしています)の、2種類のステレオタイプな子ども像が現代人の頭にはあるのではないでしょうか?
そして、当の子どもたちは、なれるものなら間違いなく、前者になりたいと望んでいるはずです。
しかし教科書のなかでは、「勉強が好きな子ども」しかこの世に生息していないことが、人々に違和感を抱かせているのです。
2.古語あるいは漢文で書かれているので、そのフィルターがかかっている
「勉強が大好きな昔の人」の代表格は孔子の「論語」ですが、このような文章は漢文もしくは古語で書かれている、ということも、非常に重要なポイントです。
「昔の堅苦しい言葉」=「堅苦しい内容」という思い込みから、人々はその内容が自分たちとは遠く隔たったものである、という意識を持ってしまうのです。
こういうものをポップな文体で書き換えたものが文学的に上質なものばかりというわけではないですが、かといって小難しいものはやっぱり子どもたちに敬遠されがちです。
3.昔の人は本当に勉強が好きだったが、現代人にはその感覚が理解できない
なにしろ、特に中国では結構な金持ちに限っては科挙を受けることができましたし、日本でも江戸時代は庶民の教育水準が高く、飢饉などが日常茶飯事のあの時代においては、勉強ができることは食いっぱぐれないことに直結していました。
しかし現代では、まったく働かなくても何らかの救済措置(親の扶養、生活保護その他)が受けられ、ひとまず餓死する確率は非常に低いのです。極端に言えば、勉強なんてできなくても最低限の生活はできてしまう、ということです。
「勉強のできる良い子」ばかりの世界観から脱却しよう
こういう子ども像は、子どもたちからの教育への信頼度を著しく低下させます。すなわち、信用できない内容を載せている教科書は子どもたちに信用されません。
というか、「勉強の好きな子ども」を教科書に載せれば実際に勉強が好きな子どもが増えるなんて、なんとも浅はかですよね。
いまこそ、「勉強が嫌いな子ども像」を教科書に反映させましょう。